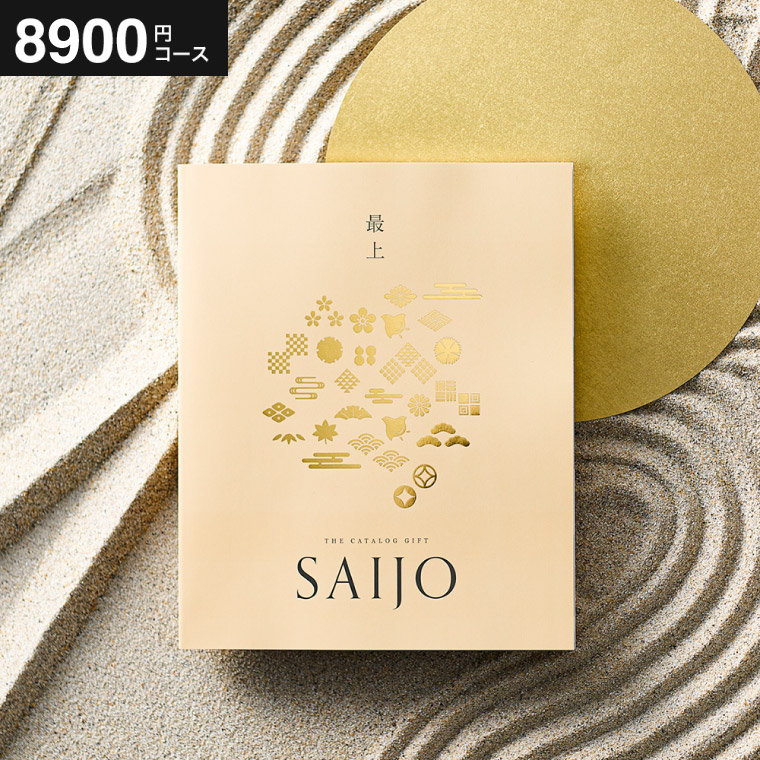出産のお祝いをもらったら、内祝いとしてありがとうの気持ちをお返しします。出産内祝いは、自分のことのように祝福をしてくれた人に対して、生まれた赤ちゃんを紹介する機会でもあります。赤ちゃんが生まれて初めて触れる内祝いという習慣。ここでは、出産内祝いを贈る前に押さえておきたいマナーとおすすめの品物、避けたほうが良い品物を紹介していきます。
押さえておきたい出産内祝いのマナー

出産祝いを頂いたら贈る出産内祝い。出産内祝いを準備する前に、押さえておきたいマナーについて紹介します。
贈る時期は?

出産内祝いを贈る時期は、一般的には赤ちゃんが生まれて1ヶ月頃に行うのお宮参りの時期とされています。 遅くなってしまった場合でも、2ヶ月以内には贈るのが望ましいです。出産内祝いの場合、赤ちゃんの体調やママの体調も優れないときがあります。予定通りにいかず、内祝いの準備が遅くなってしまった場合は、「内祝いが遅くなり申し訳ありません」という一文を添えたメッセージカードと一緒に内祝いを贈るようにしましょう。
金額相場は?

出産内祝いの金額相場は、頂いたお祝いの金額によって変わります。一般的には、頂いたお祝いの半額~3分の1の金額を目安に考えてみましょう。例えば10000円の出産祝いを頂いた場合は、内祝いの予算は3000円~5000円程度になります。目上の人からや身内から高額なお祝いをもらった場合は、3分の1よりも少ない金額の品物をお返しする場合もあります。相手との関係性にもよりますので、十分考慮して準備しましょう。
以下の記事では、出産内祝いの金額相場について詳しく解説しています。
渡し方は?

基本的には出産祝いを頂いた人に直接会ってお礼を伝えながら手渡しするのがマナーです。しかし、遠方に住んでいたりなかなかタイミングが合わない場合は内祝いを郵送することも検討してみましょう。最近では、お祝いや内祝いを郵送で贈る人が増えています。メッセージカードを添えたり、内祝いとしての体裁をしっかり整えて郵送すれば失礼に当たることはないので安心して贈ると良いでしょう。
出産内祝いののしの掛け方について

出産内祝いを贈る前に欠かせないのが、内祝いの品物に掛けるのし紙です。内祝いを贈るときには必ず掛けるようにしましょう。
のしの掛け方には、2種類あります。包装紙の内側(商品に直接かける)に掛ける「内のし」と、包装紙の外側に掛ける「外のし」です。一般的に出産内祝いは控えめな印象が与えたほうが好まれるので、包装紙の内側に掛ける内のしで用意しましょう。しかし、のしの掛け方については地域性もあるので、準備する前に確認しておきましょう。
出産内祝いの熨斗(のし)は?
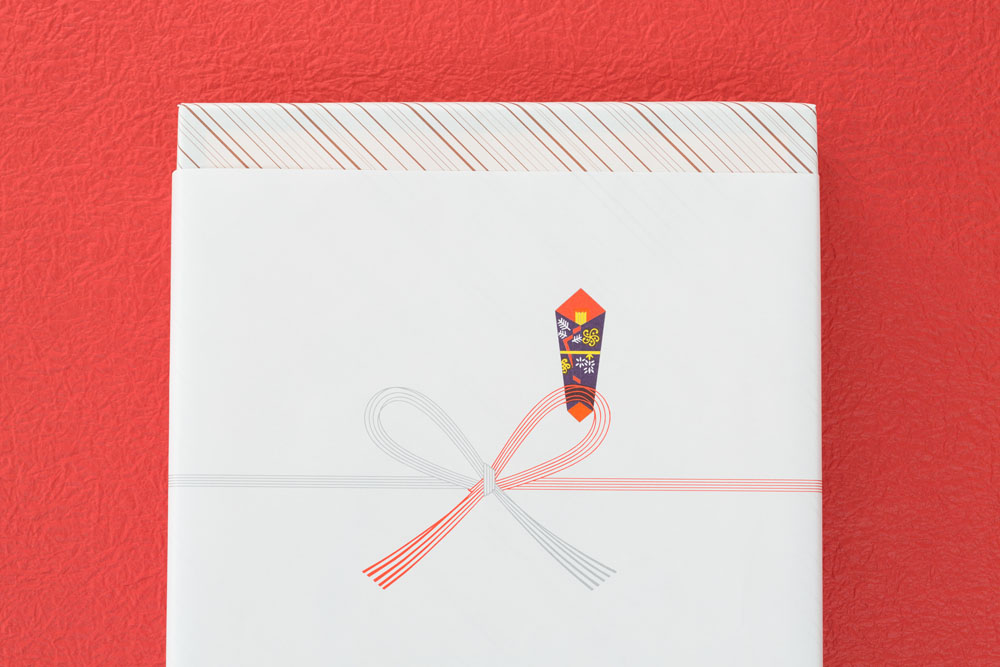
出産内祝いののしには、「出産内祝」または「内祝」と書き、のしの下側には赤ちゃんの名前を書きます。のしには、赤ちゃんの名前をお披露目するという意味も込められているので、赤ちゃんの名前には必ずふりがなをつけましょう。
熨斗の種類はどうすればいい?
のしには、いくつかの種類があります。のしの種類によっては、用途にふさわしくないものがあるので注意しましょう。出産内祝いには紅白蝶結びの水引が描かれているのし紙を使用します。「蝶結び」は何度も結び直せるという意味から出産や新築のような「何度繰り返してもうれしいこと」に使用されます。
以下の記事では、内祝いの熨斗について詳しく解説しています。
出産内祝いを準備する前にお礼状を書こう

出産祝いを頂いたら、まずお礼状を書きましょう。お礼状は、内祝いの品物を渡す時に添えるメッセージカードとは異なり、しっかりとマナーを守って書く必要があります。ここからは、お礼状に書くべき内容、お礼状の書き方、差し出すタイミングなどを紹介していきます。
お礼状には何を書けばいいの?

お礼状には、まずお祝いを頂いたことへの感謝の気持ちを書きましょう。その後、生まれた赤ちゃんの名前や性別を書きましょう。名前の由来を書くのもいいですね。
次に母子の健康状態、相手の体調を気遣う言葉や今後のお付き合いのお願いなどで締めくくると良いでしょう。
お礼状を出すタイミングは?

お礼状は、お祝いをもらってからすぐに送るようにしましょう。できれば3日以内を目安に送りましょう。お祝いに対するお礼なので、メールやLINEではなくしっかりとしたお礼状で送るのがポイントです。電話番号を知っている相手なら、お礼状を贈る前に電話で先にお礼を伝えるのもいいですね。少なくとも、メールなどで終わらせないようにしましょう。
内祝いの品物に添えるメッセージカードの書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
出産内祝いを贈る前に注意したいこと

出産内祝いを贈る時には、気をつけておきたいことがあります。知らず識らずのうちに失礼なことをしてしまわないように、気をつけておくべきポイントを押さえておきましょう。
お祝いをもらったらすぐにお礼の連絡をする
先程も説明したとおり、お祝いを受け取ったらすぐにお礼の連絡をしましょう。お祝いを直接受け取った場合はその場で伝えることが出来ますが、郵送や人づてに受け取った場合は、電話でお礼を伝えた後、お礼状を送りましょう。
できるだけ早く内祝いを贈る
お祝いや内祝いには、贈るべき時期があります。産後の新生児との慣れない生活にバタバタすることもあるかもしれませんが、内祝いは出来るだけ早く贈るように心がけましょう。最低でも2ヶ月以内に贈る方が良いとされていますが、どうしても遅くなってしまいそうな場合は、事前に連絡を入れておくことをおすすめします。
地域独自のマナーを把握しておく
お祝いや内祝いなどの昔からの習慣は、地域性の強く影響しています。一般的に決められていたことでも、その地域で決められていることが違う場合は、その地域で決められたことで準備しましょう。内祝いなどの慣習は、地域独自のしきたりが強く根付いていることもあります。両親や家族と相談して決めましょう。
出産内祝いはどんなものが喜ばれる?

出産内祝いで喜ばれる品物は、使うと消えていく“消えもの”と呼ばれる、焼き菓子やタオル、洗剤といった日用品です。他にも相手に好きなものを選んでもらえるカタログギフトは、出産内祝いに限らず、内祝いの定番となっています。
その年その年で、トレンドや人気のアイテムも変わり増えていく時代。相手に好きなものを選んでもらえるカタログギフトや商品券、金券なども人気があります。
出産内祝いに避けたほうが良い品物は?

日本では、慶事で避けたほうが良いとされる品物があります。知らないうちに選んでしまうことがないよう、出産内祝いを準備する前にチェックしておきましょう。
まず、法事や葬儀など、仏事で使用される日本茶や緑茶などは避けたほうが良いとされています。他にも、「縁を切る」という意味でギフトに不向きだとされている包丁やハサミなどの刃物も避けたほうが良いでしょう。中には「未来を切り拓く」という意味で結婚関連で選ばれることもありますが、避けるほうが無難でしょう。靴や靴下など足元に使用するギフトは、目上の人への贈りものに選ぶと、相手を踏むという意味に捉えられるので避けられています。また、パジャマや肌着などの寝具は、病気を連想させたり「着るものにも困るほど生活苦なのか」と受け取れることから、内祝いに避けられています。これらは昔から言われていることなので、最近ではあまり気にする人は居ないかもしれませんが、予め避けておいたほうが無難でしょう。
以下の記事では、出産内祝いのタブーについて解説しています。
基本的なマナーを押さえて感謝の気持を伝えよう

赤ちゃんが生まれ、出産祝いを受け取って初めて触れる出産内祝いの習慣。慣れないことでまず何から用意すればいいのか困惑してしまうでしょう。お祝いを頂いたら、まずはお礼を伝えましょう。その後、お祝いの金額から内祝いの予算を考え、相手の好みを考えながら内祝いを選んでみましょう。大切なのは、感謝の気持ちを伝えたいという気持ちです。最低限のマナーを押さえて、喜ばれる内祝いの品物を選びましょう。