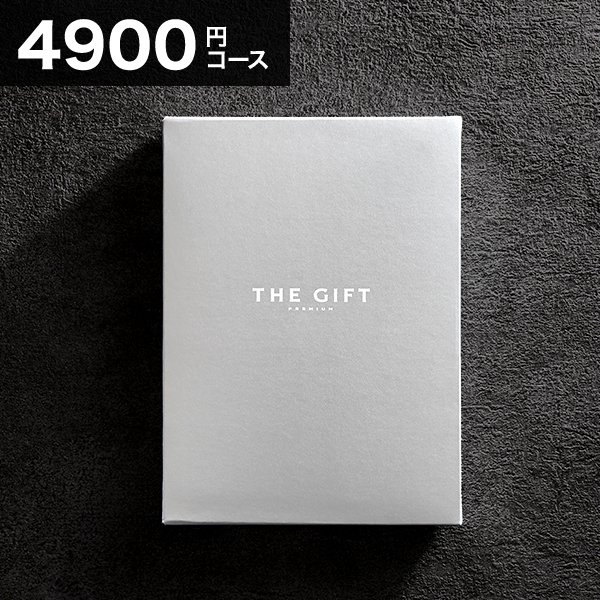いただいたお祝いのお礼や幸せのお裾分けとして内祝いを贈る場合、その相場がいくらか知りたいという人も多いのではないでしょうか。相場が分かれば、贈るものも大体の目星がついてきます。内祝いを贈るときは、相場を考えつつ、自分にとって無理のない範囲で気持ちを伝えることが大切です。
この記事では、内祝いを贈る際に気を付けておきたいマナーも含めて、その相場を紹介していきます。
出産内祝いの相場はいくら?
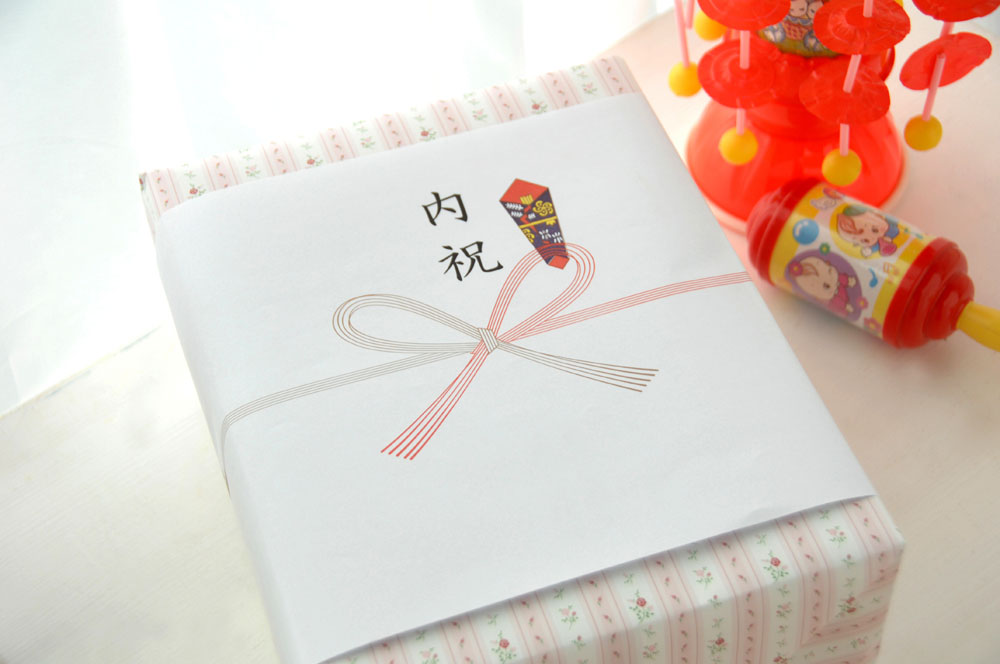
基本的には内祝いの金額を考えるうえで、半返しというマナーが存在することを覚えておきましょう。半返しとは、いただいたお祝いの半額程度のものをお返しするという、内祝いを贈るうえで相手に配慮した大切なマナーの一つです。
半返しを意識することで、相手に気を遣わせることなく、お互いに気兼ねなくいられるようになるといえます。
たとえば、出産のお祝いには1万円ほどのものをいただくケースも多いです。その場合には、内祝いは3000~5000円ほどのものを用意するといいでしょう。また、1万円以上のお祝いをいただいた場合には、内祝いは3分の1ほどにするケースもあります。あくまで大切なことは、自分にとって無理のない範囲で相手にお返しするということです。高価なものをいただいたからといって、すべてを半返しでお返しする必要はありません。金額ももちろん重視しておきたいことではありますが、相手が喜んでくれるものを第一の基準として内祝いを選びましょう。
また、連名でお祝いをいただいたり、お祝いの金額がいくらかわからなかったりする場合も、もちろん考えられます。
まず、連名でいただいたとしても、それぞれ個人宛てに内祝いを贈るのが一般的な常識とされています。そのうえで、この場合にはこちらもあまり深くは考えずに、1000円程度のプチギフトを贈っても問題ありません。特に、連名や、さほど値段も張らない花束などは、相手も気持ちとしてお祝いを贈っているケースがほとんどです。相手の気持ちをくみ取って、タオルや、皆で分けられるお菓子などが喜ばれることも多いでしょう。その場合に、お礼の手紙やギフトカードなどを添えると、より気持ちが伝わりやすくなります。
また、出産内祝いの場合は特に、自宅に招くことで内祝いに代えて気持ちを伝えてもいいでしょう。生まれてきた赤ちゃんのお披露目の場として、まさに幸せのお裾分けとして自宅に招いておもてなしすることは、出産の内祝いだからこそできることです。もちろん自宅に呼べる間柄かどうかは重要ですが、気持ちを伝える方法は、ものを贈るだけではありません。形に残らない分、相手も気を遣わずに遠慮なく受け取ってくれることがほとんどでしょう。
結婚内祝いの相場はいくらくらい?

結婚のお祝いは、基本的にご祝儀としていただくケースが多いです。特に式や披露宴を行う場合は、ご祝儀袋に包んで結婚のお祝いという形で式当日にいただくことがほとんどです。もちろん関係性によって金額はさまざま変わりますが、その相場は3万円ほどであるといわれています。よって、結婚の内祝いには、半額~3分の1程度の1万~1万5000円ほどが相場になると考えて間違いではありません。それを引き出物に代えて贈る人も大勢います。
また、披露宴に出席しているしていないに関わらず、ご祝儀袋に入ったお金以外にも、お祝いをいただくこともあるでしょう。もちろんその場合には、感謝の気持ちを伝えるためにも、別で内祝いを用意するようにしましょう。たとえば、5000円ほどのお祝いをいただいた場合には、2000円から2500円ほどの内祝いが適切だといえます。式のあとにいただいた場合は、新婚旅行のお土産を内祝いとして贈るのも一つの手です。旅行先でも考えてくれたとして、相手に気持ちも伝わりやすいという利点もあります。
上記のように、基本的な結婚内祝いの相場はありますが、家族からのお祝いの場合など、特別な間柄のときはもちろんその限りではありません。家族からお祝いをいただく場合、家族間でのルールがあることも多いです。
そもそも内祝いを贈ることはなしだったり、贈っても金額が決まっていたりすることもあるでしょう。
また、特に親から結婚祝いをいただく場合、今後の生活支援という意味合いも含めて、高額な資金援助や高価なものをいただくこともあります。その場合には、半返しなどは意識せず、感謝の気持ちを込めて内祝いを贈ることも大切です。
場合によっては、親に直接相談してみるのも一つの手といえるでしょう。
内祝いを贈るタイミングや贈り方

出産や結婚の内祝いを贈るタイミングや贈り方には、いくつかの相手を思いやるマナーがあります。
まず、基本的には、お祝いをいただいてから1カ月以内を目安に贈ることを心掛けましょう。相手が忘れたころに贈っても、何に対するプレゼントか分からずかえって失礼になってしまうことも考えられます。ただし、早過ぎるのもあまり好ましいものではありません。もちろんある程度の目星はつけておいて正解ですが、特に結婚式後や出産後などはなにかと慌ただしいものです。その中でじっくりと内祝いのものを選ぶことは難しいでしょう。相手の好みのものをしっかりと選ぶためにも、ある程度の準備期間を設けたうえで、気持ちよく贈るようにしましょう。
また、もっとも内祝いの贈り方で丁寧とされるのは、やはり手渡しです。直接感謝の言葉とともに渡すことができるので、相手に気持ちを伝えやすいというメリットがある点からも、手渡しは有効な手段といえるでしょう。しかし、当然タイミングなどによって手渡しできないことも考えられます。たとえば、遠方に住む親戚や友人なども手渡しするのは難しいでしょう。
その場合には、郵送で贈るのも一つの手です。ある程度相手の都合のいい時間帯を把握しておけば、迷惑になることもありません。その際には、感謝の気持ちを手紙として添えるなどすると、よりいいでしょう。のしや、水引なども適切なものをしっかりと選んでつけることが大切です。お店などで購入する場合は、内祝いだということを伝えると、それに適したのしなどを選んでくれます。
一カ月以内が内祝いを贈るときの基本ではありますが、もちろん時と場合によるということには注意が必要です。
たとえば、相手が弔事などの場合にはしっかりとタイミングを見計らいましょう。相手が弔事の場合でも、贈ること自体は間違いではありません。ただし、一般的には、四十九日を過ぎたころがもっともいいタイミングとされています。
そのほか、のしの表書きには「祝」という字は極力避けて、「お礼」と表記することがベストです。また、タブーとされているものも柔軟にとらえて選ぶ人も増えていますが、弔事の人に対しては、特に配慮することを心掛けましょう。たとえば苦しみなど悪いことを連想させてしまうくしや、弔事の際に用いられる緑茶などは避けた方が無難です。
より繊細に相手の状況を理解することが大切だといえます。
内祝いの品物選びに困ったら?

いただいたものを調べても金額がいくらか分からなかったり、これまでの関係性から考えて適切なものが思い浮かばなかったりして、内祝いに何を贈ろうか困る場合もあります。内祝いに困った場合には、カタログギフトを選んでもいいでしょう。ある程度金額をぼかすことができるので、何を贈っていいのか分からない場合に適切なのがカタログギフトといえます。種類が豊富なものを選べば、相手も商品を選ぶのに困ることはないでしょう。ただし、カタログギフトは相手に負担が増えるということは頭に入れておかなければなりません。人によっては、商品を選ぶこと自体が面倒だと感じることもあります。また、はがきやインターネットから応募することを手間に思う人も、中にはいます。カタログギフトを贈る場合は、贈る相手をしっかりと見極め、目上の人には贈らないようにするのが無難です。
カタログギフトを贈ることが好ましくない場合、形に残らない消えものと呼ばれるものを贈るのも一つの手です。たとえば、高級なお菓子のセットや洗剤のセットなど、自分では普段買わないけれど、あれば嬉しいものを贈るといいでしょう。子どもがいる家庭に贈る場合は、ジュースの詰め合わせや、子どもの好みに合わせたレトルトなども喜ばれるものの一つです。ただし、食品などを贈る際には、アレルギーがないかどうかに十分注意しましょう。不安な場合は、用意する前に一度確認してしまっても問題ありません。万が一の事故を起こしてしまうよりかははるかに得策です。
食品だけでは物足りないという人は、商品券などもセットにすると、より喜ばれることもあります。特に親世代には人気のセットです。ただし、商品券などは相手が自分で買いに行く必要があります。そのため、カタログギフトと同じように手間がかかってしまうということは、やはり念頭に置いておくべきです。また、商品券が使える場所はしっかりと把握しておきましょう。もし、相手の生活圏内に商品券を使える場所がない場合、かえって失礼になってしまうこともあり得ます。相手の生活範囲と商品券の使用可能場所がしっかりリンクしている場合に商品券を贈るようにしましょう。
さらに、一つ気にしておきたいことは、商品券は金額が一目で分かるというデメリットがあるという点です。場合によっては、相手からいただいたものよりはるかに下回る、もしくは上回る金額の商品券を贈ってしまうことにもなります。相手に気を遣わせたり、不快に思われたりしないように、できるだけ配慮をして贈るようにしましょう。
内祝いのマナー違反はある?

マナーを守らずぶしつけに内祝いを贈ることは、かえって相手にいやな思いをさせてしまうことにつながります。感謝の気持ちでも、幸せのお裾分けでも、しっかりと気持ちを伝えるために、マナーは必ず守るようにしましょう。内祝いを贈る際のマナーとしては、まず、いただいたお祝いより高価な内祝いを贈ることは好ましくないとされています。よかれと思って高価なものを贈っても、反対に相手に気を遣わせてしまう可能性があるためです。ただし、いただいたお祝いの3分の1以下の価格の内祝いを贈ることも、場合によっては、いいとはいえません。もちろん、金額がすべてではありませんが、露骨に相手に3分の1以下の金額が伝わってしまうものは避けておきましょう。
のしや包装、挨拶状などをつけないで内祝いを贈ることもマナー違反の一つとされています。それらを付けないと、何のお祝いか相手に伝わらないことも十分にあり得ます。前述の通り、忘れたころに内祝いを贈ることも同様です。
また、のしにはしっかりと表書きを記すようにしましょう。「祝」という字や「お礼」という表記にするほか、出産の内祝いの際には、生まれてきた赤ちゃんの名前のみを表書きに記すことがルールとされています。それが、赤ちゃんの名前を正式に公表することと同じ意味になります。相手により丁寧さを伝えるためにも、細かい部分までこだわることを意識しましょう。
そのほかにも、友人経由で内祝いを贈ることはタブーとされています。親しい間柄であっても、できる限り自分で渡して気持ちを余さず伝える工夫をすることが大切です。
内祝いでもらって喜ばれるものは何?

内祝いとしてもらって嬉しかったもののアンケートでも、カタログギフトは安定した人気を誇ります。前述の注意点に気を付けながら贈れば、ほとんどの人に安定的に喜んでもらえるものといって過言ではありません。迷った場合には、カタログギフトで統一しても、さほど問題はないでしょう。
そのほかにも、名入れされていない上質なタオルなども考えられます。ただし、タオルは一般的にもよくプレゼントとして使われるものです。特に年配の人は、プレゼントとして何度ももらっている場合もあります。その場合、商品券などであれば、ある程度自由に選択することができるので、特に年配の層に喜んでもらえるものといえるでしょう。
商品券だけでは金額が明確に分かってしまうので、クッキーやバームクーヘンなどのお菓子や高級なお米など、消えものを一緒に添えると金額をぼかすこともできます。味気なさを回避して、華やかさを演出することもできるので、気持ちをしっかり伝えたいときに有効な手段として覚えておきましょう。
結婚内祝いの品物選びに悩んだら、以下の記事を参考にしてみてください。
出産内祝いにおすすめのギフトは、以下の記事を参考にしてみてくださいね。
相場を踏まえて内祝いを選ぼう!

内祝いには、一般的な相場やマナーなどがいくつかあります。すべてがすべて相場やマナーを守る必要はありませんが、あまりにも基準から離れてしまうと、かえって失礼に思う人も少なくありません。相手も自分も嫌な思いをしてしまわないよう、しっかりと一般的な基準を踏まえたうえで、相手を思った内祝いを選ぶようにしましょう。